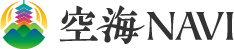鷺井神社の祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)、以前は青龍明神と呼ばれていました。また、明治以前は雨乞い祈願に由来する青龍大権現と呼ばれ、弘法大師空海が唐から帰ってきた後に創建し、唐の青竜寺にちなんで名付けた寺であったといわれています。
境内にある青龍古墳は、5世紀後半に築造された2段築成の円墳で、幅の広い周庭帯と呼ばれる平坦地が古墳を取り囲んでいます。これを含めると全長78mで、県内の円墳としては他に見られない大きさになります。また、古墳の外側には中世の戦で掘られた濠跡もあり、さまざまな時代の痕跡が積み重なって現在の姿になっています。
神社の100mほど東には「鷺の井(さぎのい)」と呼ばれる泉跡があります。この泉跡には「あるとき片羽の青鷺がおり、三日三晩羽を休めたところ翼が治り飛び去った。その跡からは清水が湧き出し、神託で眼病に効果があることが告げられ神水として崇められた。鷺が飛び去った後の境内には珍しい「片葉の葦」が自生し始めた。」という古い伝承があります。
周辺では今も「片葉の葦」を見ることができます。

上空から見た鷺井神社・青龍古墳

墳丘(左)を囲む広い周庭帯